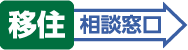昔、そう、五十何年か前だ。売られて行く牛を見た。ふるさとは島。だから牛も肉になる時は海を渡る。小さな船に、小さなハシケが掛けられて、男が手綱を引き、もう一人が牛の尻を叩く。牛はモウと幾度か泣き、脚を踏ん張った。十歳の少年は、幅の狭いハシケから牛が足を踏み外さないかと心配し、その目に涙が光っているようにも感じたのだが、後に、牛の瞳は常に涙に似た潤いが保たれているのだと知る。
昔、そう、五十何年か前だ。売られて行く牛を見た。ふるさとは島。だから牛も肉になる時は海を渡る。小さな船に、小さなハシケが掛けられて、男が手綱を引き、もう一人が牛の尻を叩く。牛はモウと幾度か泣き、脚を踏ん張った。十歳の少年は、幅の狭いハシケから牛が足を踏み外さないかと心配し、その目に涙が光っているようにも感じたのだが、後に、牛の瞳は常に涙に似た潤いが保たれているのだと知る。
その頃、牛肉が食べられるのは盆と正月だけだった。それも、最後の方の鍋底は、牛肉の味が染みたネギや糸コンニャクだらけ。別れた女との甘い記憶を男がたぐる、あの遠い過去の感傷みたいに、ネギを噛みつつ肉を偲んでいたのだ。ああそれが、なんという豊かさか。いま僕は、牛、豚、鶏を毎週「四・二・一」の割合で日々欠かさず食べている。鶏だけが自家産で、自分の手で捌く。
 僕は鶏の目を見ない。遠くの空に視線を向け、侍が刀を抜く格好だ。言うならばブラインドタッチで首をひねり、脚を切り、腹を裂き、たちまちにして肉とする。目と目は、なんとしても合わせたくない。餌の袋を持てば駆け寄り、近くを通れば挨拶らしき鳴き声を発し、飼主の僕を疑うこと微塵もなかった鶏たちだ。飼主に命を奪われるなんて、鶏にすれば夢であってほしい。その「夢」を夢としてやるため、僕の包丁さばきは目にも止まらぬ早業となる。そしてつぶやく。すまん、ありがとう。
僕は鶏の目を見ない。遠くの空に視線を向け、侍が刀を抜く格好だ。言うならばブラインドタッチで首をひねり、脚を切り、腹を裂き、たちまちにして肉とする。目と目は、なんとしても合わせたくない。餌の袋を持てば駆け寄り、近くを通れば挨拶らしき鳴き声を発し、飼主の僕を疑うこと微塵もなかった鶏たちだ。飼主に命を奪われるなんて、鶏にすれば夢であってほしい。その「夢」を夢としてやるため、僕の包丁さばきは目にも止まらぬ早業となる。そしてつぶやく。すまん、ありがとう。
いま、すべてが悲しい。
放射能に汚染された牛を出荷した農家が悲しい。
放射能に汚染された稲ワラを出荷した農家が悲しい。
気付いたときにはその肉が全国に流通していたという事実が悲しい。
それを知らずに売ったスーパーが悲しい。
そうとは知らずに客に出した焼肉店が悲しい。
園児や生徒の給食に出したという保育園と小学校が悲しい。
我が子を案ずる母の心が悲しい。
在庫をさばけないと嘆く食肉業者が悲しい。
高級ブランド牛までが風評被害に巻き込まれつつある産地が悲しい。
閑散とした家畜セリ市場が悲しい。
一気に暴落した市場価格が悲しい。
出荷停止を指示した行政が悲しい。
廃棄処分する肉は政府の買い上げとすると声明した国家が悲しい。
●
でも、僕には別な悲しみがある。牛自身の悲しみを想う悲しみだ。せっかく立派な体に成長したのに、人間の腹を満たすという本来の役目を果たせないまま、焼かれ、灰になる。本当は放射性セシウムなんて含まれていない肉だってあるのに、牛肉というだけで人間に恐れられてしまう牛が悲しい。
僕の悲しみをさらに募らせる場面もある。出荷自粛で牛舎に残った牛たち。テレビカメラが映し出す肉牛たちは、世界の驚きと動揺と悲しみ、ときに怒り、そのわけをまるで知ることのないまま、今日もゆるやかにワラを食んでいる。その目の潤い、その鼻先の湿り具合。それは十歳の少年がふるさとの海で見たあの顔に似てはいないか。
●
 最後に、僕にはもうひとつの悲しみがある。人は「レベル7が及ぼした影響」をいま恐れている、嘆いている、憤っている。むろん現在の状況をして当然の心理ではあろう。が、「牛になろうとする人」はなぜか少ない、それが僕の最後の悲しみだ。肥育農家は常に心の内でありがとうと牛に言っている。同じように、それを食べ物として口に入れている人間にも「ありがとう」の気持ちがあって欲しい。フランス映画で、いっさいのナレーションなしに人間の食料となる家畜の一生を淡々と追うドキュメンタリーを僕は見たことがある。電気ショックを与えて絶命させる係の男に、そうとは知らず、次の瞬間死ぬのだということももちろん知らず、彼に鼻先を寄せ、ジャレつく牛がいた。その瞬間、僕の目に薄く涙がにじんだ。とともに、人間を生かすために死んでいく牛にありがとうとテレビの前でつぶやく自分もいた。
最後に、僕にはもうひとつの悲しみがある。人は「レベル7が及ぼした影響」をいま恐れている、嘆いている、憤っている。むろん現在の状況をして当然の心理ではあろう。が、「牛になろうとする人」はなぜか少ない、それが僕の最後の悲しみだ。肥育農家は常に心の内でありがとうと牛に言っている。同じように、それを食べ物として口に入れている人間にも「ありがとう」の気持ちがあって欲しい。フランス映画で、いっさいのナレーションなしに人間の食料となる家畜の一生を淡々と追うドキュメンタリーを僕は見たことがある。電気ショックを与えて絶命させる係の男に、そうとは知らず、次の瞬間死ぬのだということももちろん知らず、彼に鼻先を寄せ、ジャレつく牛がいた。その瞬間、僕の目に薄く涙がにじんだ。とともに、人間を生かすために死んでいく牛にありがとうとテレビの前でつぶやく自分もいた。
今の状況は、牛に対してありがとうであると同時に、大変だけどがんばろうね、そのねぎらいの時でもあろうかと僕は思う。人の命を保ってくれている生き物たちの心を想う絶好の時でもあろうかと思う。