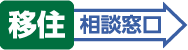いつだったか若い女性がダンプカーを運転している姿をテレビで見た。軽い衝撃を受けた。ダンプといえば、いかつい男が頭にタオルを巻き、砂煙を上げて走る、そんなイメージがあったからだ。しかし時代は変わっている。男は仕事。女は家事と育児。それはもう時代の流れに合致しないのに、女性のダンプごときで驚いたのは、僕の意識がギリギリ古い世代に属しているということかもしれない。
いつだったか若い女性がダンプカーを運転している姿をテレビで見た。軽い衝撃を受けた。ダンプといえば、いかつい男が頭にタオルを巻き、砂煙を上げて走る、そんなイメージがあったからだ。しかし時代は変わっている。男は仕事。女は家事と育児。それはもう時代の流れに合致しないのに、女性のダンプごときで驚いたのは、僕の意識がギリギリ古い世代に属しているということかもしれない。
今年は妙な天気の連続だった。暖かい冬から一転し、春の始めが寒かった。梅、アンズ、スモモの結実が悪かった。残り少ない実は大風で吹き飛ばされた。大風は一度ならず三度までも。とことん吹いて、例年なら持て余すほどなるスモモが一粒残らず、すっからかんになった。
 しかし悪いことばかりではない。僕はこの原稿を五月も残り少なくなった頃に書いているが、今年の五月は天国のようだった。湿度は十%台。昼間の光は首筋を焼く。だが、夜はほどよく空調された高級ホテルの部屋のように快適。グッスリ眠れた。
しかし悪いことばかりではない。僕はこの原稿を五月も残り少なくなった頃に書いているが、今年の五月は天国のようだった。湿度は十%台。昼間の光は首筋を焼く。だが、夜はほどよく空調された高級ホテルの部屋のように快適。グッスリ眠れた。
そんな五月のある日、椎の木に登って枝打ちをした。高さ十メートル余。ちょっと危険だが、延長梯子を立てて登ることにした。椎の木が作る日陰が甚だしく、下にある柚子や柿が喜ぶ顔を見たかったのだ。幸いなことに僕は高い所を苦にしない。
 キャベツ畑をモンシロチョウが舞う。キャベツの数は五百ほど。悪いけど死んでもらいます。青虫は毎日、指でつぶす。南風が吹いている。物を吹き飛ばすほどの強さではないが、杉と山桜と孟宗竹が揺れている。僕のそばにいる人がつぶやく。海にいるみたいな気がするわ。海辺の暮らしなんて知らないくせに変だよね。でもたしかに…わたしにはこの風の音が海の音に聞こえる。
キャベツ畑をモンシロチョウが舞う。キャベツの数は五百ほど。悪いけど死んでもらいます。青虫は毎日、指でつぶす。南風が吹いている。物を吹き飛ばすほどの強さではないが、杉と山桜と孟宗竹が揺れている。僕のそばにいる人がつぶやく。海にいるみたいな気がするわ。海辺の暮らしなんて知らないくせに変だよね。でもたしかに…わたしにはこの風の音が海の音に聞こえる。
僕の父は魚の仲買人だった。瀬戸内海で獲れた魚を関西に出すのが仕事だった。浜には数多くの生簀があり、蛸や鱧や鯛が泳いでいた。生簀から生簀に跳び移る時、父は誤って海に落ち、ずぶ濡れになって帰ってきたこともあった。そんな父の顔は海の潮に焼けて黒く光っていた。一合五勺の酒に酔うと、黒い顔に太く、深い皺ができた。
 十四歳まで瀬戸の島で暮らした僕は、海の風をいっぱい受けた。父の酔った顔からも潮風をもらった。あれから六十年。父がよく作ってくれた鯛の潮汁をいま頻繁に作る。出刃包丁を持って鯛を捌く僕を見て、そばにいる人が感心する。ネギをたっぷり入れた熱い潮汁をすすりながら、瀬戸の海を語り、父が喉に引っ掛けるなと言った鯛の骨の危険を語り、海からの風を、僕は、彼女に語る。そして思う。ひょっとしたら…。
十四歳まで瀬戸の島で暮らした僕は、海の風をいっぱい受けた。父の酔った顔からも潮風をもらった。あれから六十年。父がよく作ってくれた鯛の潮汁をいま頻繁に作る。出刃包丁を持って鯛を捌く僕を見て、そばにいる人が感心する。ネギをたっぷり入れた熱い潮汁をすすりながら、瀬戸の海を語り、父が喉に引っ掛けるなと言った鯛の骨の危険を語り、海からの風を、僕は、彼女に語る。そして思う。ひょっとしたら…。
「海なんかここにはないのに、わたしは都会しか知らないのに、畑の風の音が海風みたいに聞こえる。変だよねえ」。そう言う彼女のあの空耳は、ひょっとしたら…僕が繰り返し語り、伝えてきた海物語、頻繁に作る鯛の潮汁の香り、そのせいかもしれないと。
 キャベツの青虫取りが終わった。サツマイモ苗三百本の畝立て、落花生とトウモロコシのポットまき。大いなる汗をかいた。ルバーブと苺を混ぜたジャムを口に含み、木陰で熱いお茶を飲む。南風は高い木々をまだ揺らしている。しかし木陰を抜ける風は背中の汗をほどよく乾かすくらいに柔らかい。湿度は今日も低い。僕はジョークを飛ばす。この前の大風は憎たらしいが、その後の天気は完璧だ。いくらかカネを払ってもいいくらい素晴らしいぜ。
キャベツの青虫取りが終わった。サツマイモ苗三百本の畝立て、落花生とトウモロコシのポットまき。大いなる汗をかいた。ルバーブと苺を混ぜたジャムを口に含み、木陰で熱いお茶を飲む。南風は高い木々をまだ揺らしている。しかし木陰を抜ける風は背中の汗をほどよく乾かすくらいに柔らかい。湿度は今日も低い。僕はジョークを飛ばす。この前の大風は憎たらしいが、その後の天気は完璧だ。いくらかカネを払ってもいいくらい素晴らしいぜ。
 そして僕は考える。働くとはどういうことかと。労働の対価としてお金がいっぱい入る、それが目的であり理想であることは間違いない。加えて、もし、もうひとつの理想があるのだとすれば、それは、肉体が心地よいぞと声を発する瞬間を労働の中に得ることではないか。
そして僕は考える。働くとはどういうことかと。労働の対価としてお金がいっぱい入る、それが目的であり理想であることは間違いない。加えて、もし、もうひとつの理想があるのだとすれば、それは、肉体が心地よいぞと声を発する瞬間を労働の中に得ることではないか。
五月の風は、今日なすべき仕事をほぼ終えた夕刻、僕の体の奥の細胞に、歓びの声を上げさせる。シンプルだが、それは確かな声だ。小さいけれど、大きい幸せの時だ。さて風呂、一合五勺の晩酌。陽に焼けて真っ黒な顔、髪がめっきり薄くなった頭頂部。僕はすっかり父に似てきた。