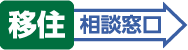暖冬としきりに騒がれる。どこも桜の開花が早い。暖かい冬はすっかり定着した感じ。満開の桜。母に手を引かれる小学校の入学式。あの情景はもう消えてしまうのか。
暖冬としきりに騒がれる。どこも桜の開花が早い。暖かい冬はすっかり定着した感じ。満開の桜。母に手を引かれる小学校の入学式。あの情景はもう消えてしまうのか。
少し寂しいか。しかし年取ると暖冬といわれるくらいがちょうどいい。出荷のために野菜を水洗いする。寒さ、冷たさは濡れた手だけにとどまらず、全身が凍える。だから春を恋する気持ちは年ごとに強まる。4月の声を聞くだけでうれしい。ウグイスの声、ヒバリの声、コジュケイの声を聞けば心が浮き立つ。そしてキウイの花、アケビの花、さらにその甘い香りが加わると春の役者はそろう。手にした鍬を仮想パートナーとし、僕はワルツを踊ったりする。
 僕を百姓にしたのはヒバリの鳴き声だったかもしれない。35年前、農村風景を色濃く残す手賀沼畔の団地に住んでいた。日曜日ごと、沼を巡る長い道をランニングした。頭上でしきりとヒバリが鳴いた。日本人の90%がかつては農民だった。ゆえに多くの人の体には百姓遺伝子が潜んでいるといわれる。ただ、それを顕在化させるには具体的な「触媒」が必要かと思う。職場での行き詰まり、健康の問題、食へのこだわり、明るく広い風景による脳へのUV照射。これら触媒の数が多いほど百姓遺伝子の顕在化は劇的。僕の場合、最初に得た触媒は日曜の午後に聞いたあのヒバリの鳴き声だった気がするが、あなたの場合はどうか。
僕を百姓にしたのはヒバリの鳴き声だったかもしれない。35年前、農村風景を色濃く残す手賀沼畔の団地に住んでいた。日曜日ごと、沼を巡る長い道をランニングした。頭上でしきりとヒバリが鳴いた。日本人の90%がかつては農民だった。ゆえに多くの人の体には百姓遺伝子が潜んでいるといわれる。ただ、それを顕在化させるには具体的な「触媒」が必要かと思う。職場での行き詰まり、健康の問題、食へのこだわり、明るく広い風景による脳へのUV照射。これら触媒の数が多いほど百姓遺伝子の顕在化は劇的。僕の場合、最初に得た触媒は日曜の午後に聞いたあのヒバリの鳴き声だった気がするが、あなたの場合はどうか。
 風が吹いて桶屋は儲かり、ヒバリが頭上で鳴いて僕は百姓になった。昭和59年4月、山羊、鶏、犬、猫とともにトラックに乗り、この八やちまた街に移った。その春、子どもばかりでなく僕までも喜ばせたのは畑に鈴なりのイチゴだった。毎朝カゴを手にして収穫した。しかしずいぶん小粒で酸っぱかった。後でわかったことだが、あれは段々畑の土が流れないようにする道具だった。前住者の目的は販売ではなかったのだ。
風が吹いて桶屋は儲かり、ヒバリが頭上で鳴いて僕は百姓になった。昭和59年4月、山羊、鶏、犬、猫とともにトラックに乗り、この八やちまた街に移った。その春、子どもばかりでなく僕までも喜ばせたのは畑に鈴なりのイチゴだった。毎朝カゴを手にして収穫した。しかしずいぶん小粒で酸っぱかった。後でわかったことだが、あれは段々畑の土が流れないようにする道具だった。前住者の目的は販売ではなかったのだ。
いまやイチゴの品種は覚えきれないほど数多い。甘さ、大きさ、花の色。すべてにおいて昔とは比較にならない大改良がなされている。ピンクの花が咲く品種を僕が初めて入手したのは3年前だ。
イチゴが実る風景に最初に出合ったのは小学生のころ。同級生が町営住宅に住んでいた。どこも持ち家という昔の田舎で賃貸住宅は珍しかった。家は小さいが明るくモダン。庭にイチゴがあった。母が植えたと同級生はいった。町営住宅にイチゴ。そのときは感じなかったが、これも僕を百姓に導いた一つの触媒だったかもしれない。
 「春はあけぼの」。平安の賢女に教えられるとおり、春の夜明けはいいものである。冬はもちろんいうに及ばず、夏、秋とても、この空気の柔らかさ、シットリ感はない。さらに百姓には、夏野菜の成長を眺める朝飯前の楽しみが加わる。春は一年のあけぼの。
「春はあけぼの」。平安の賢女に教えられるとおり、春の夜明けはいいものである。冬はもちろんいうに及ばず、夏、秋とても、この空気の柔らかさ、シットリ感はない。さらに百姓には、夏野菜の成長を眺める朝飯前の楽しみが加わる。春は一年のあけぼの。
このビニールトンネルには促成栽培のカボチャがある、トウモロコシもある。まだ冷たい風だ。しかし実りの季節に向かうこの春の朝の風は希望に満ちている。氷さえ張るころ、マルチとトンネルで種を落としたカボチャのツルは黒いマルチの上に小さく横たわっている。
東の林間が赤く染まる。早起き鳥の声がこだまする。百姓はその光と風の中でじっとビニールトンネルを見る。ヒバリの声を触媒とし、隠れていた百姓遺伝子の顕在化という偶然の出来事を4月の朝に喜ぶ。